7月7日と言えば、ご存知の通り「七夕(たなばた、しちせき)」です。
ただ、こちらは意外と知られていませんが、七夕は日本だけでなく、中国や韓国、ベトナムでも同様の節供、節日となっているのです。
大人になると、それほど縁がないかもしれませんが、それでも毎年、子供たちが短冊に願いを書いたり、彦星と織姫のお話を聞いたりしているイメージはあるかと思います。
ただ、その由来や短冊の意味について、知っている人は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、七夕の「2つの由来」と短冊の意味についてお話ししたいと思います。
Sponsored Links
七夕の「2つの由来」と短冊の意味
織姫と彦星が一年に一度出会うことができる七夕は、実は二つの物語が結びつてできあがりました。
一つは中国から伝わった織女(しゅくじょ)と牽牛(けんぎゅう)の物語です。
天帝の娘である織女は、牛飼いの青年・牽牛と恋に落ちます。
ところが、あまりに愛し合い過ぎ、二人とも仕事を放棄してしまったため、怒った天帝は、織女を天の川の東に、牽牛を西に引き離しました。
打ちひしがれてなげく二人を見て、憐れに思った天帝は、一年に一度、七月七日の夜だけ二人が逢うことを許したのです。
もう一つが、日本に古くから伝わる棚機津女(たなばたつめ)の伝説です。
棚機津女は天衣を織る巫女で、水辺の機織り小屋にこもって神を待ち、神の妻となりました。
神に身を捧げることで、人々の災厄を祓(はら)ったのです。
七夕と書いて「たなばた」と読ませるのは、棚機津女からきています。
この二つの伝説が結びついて現在の七夕が生まれたのです。
笹竹に願い事を書いた短冊を飾るのは、江戸時代にはじまった風習です。
それ以前は五色の糸を飾っていました。
織女にあやかり裁縫が上達するよう願ったのです。
その糸が紙の短冊になったのは、寺子屋で習字がうまくなりますように」と子供たちが短冊を飾るようになったからです。
それが毎年受け継がれて広まっていき、現在もたくさんの子供たちの願いを天の川に流しているのです。









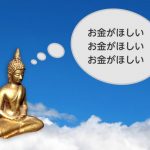


























この記事へのコメントはありません。